こんにちは、獣医師のにわくま(@doubutsu_garden)です。
獣医大学の学生生活ってどんな感じなの?
獣医学科ではどんな勉強をするの?
今日は私が過ごした獣医大学での6年間の学生生活の様子を紹介します!
受験生も終わり!いよいよ獣医学科に入学!:1年生
長い受験勉強も終わり、獣医大学合格という第一関門を突破すると、いよいよ獣医大学での6年間の学生生活が始まります。
私の大学は1学年30人ほどだったので、同級生とはすぐ仲良くなりました。
もちろんクラス替えなんかはないので、これから6年間濃密な時間を過ごすことになります。
クラスはまじめで優秀な人ばかり。さすが狭き門を突破してきた人たちというような雰囲気で、自分が置いて行かれないか不安になったものです。
でもガリ勉という感じではなく、ほどよく遊び、ノリのいい人が集まっていました。
獣医学科は横のつながりよりも縦のつながりの方が強いので、先輩たちとも仲良くなれます。
男女は半々ぐらい。
昔は男子が圧倒的に多かったですが、年々女子が増えてきて、今では7割が女子という大学もあります。
さて、授業はというと、1年生のうちは教養科目がメインで、専門科目がほとんどありません。
せっかく獣医学科に入ったのになんだかモチベーションが下がりますね。
今はだいぶカリキュラムが変わり、低学年のうちに専門科目を学ぶみたいです。
うん、そうするべきだね。
だって、受験期を乗り越えて合格し、(おそらく最も)モチベーションが高い1年生がほとんど専門科目を学べない。暇だからバイトを入れまくる。
そして高学年になって、専門科目を詰め込む。本当に6年間の授業の配分間おかしくない?って。
バイトはできる?とよく聞かれますが、
できます!というか、この時期は暇なのでほぼ全員アルバイトをしてます。
家庭教師、居酒屋、カフェが定番ですね。
動物病院でお手伝いをしている人もいました。
卒業して動物病院で働くなら、学生時代は全く違うバイトでもいいのでは?と思いますが、今から少しずつ経験しておきたい!という意識高い人もいます。
もちろん、サークルに入って飲み会や合宿も楽しめます!
獣医学科にいると獣医以外の友達がなかなかできないし、世界も狭くなってしまうので、アルバイトやサークルはおすすめです。
解剖が一番の山:2年生
2年生のメインの専門科目はなんといっても解剖学。
入学して最初にぶち当たる壁。
覚えること多すぎ!筋肉とかの名前難しすぎ!動物の種類によって体の構造が違いすぎ!
実習では牛、馬、犬、にわとりをクラス全員で一ヶ月ぐらいかけながら解剖していきます。
骨、血管、筋肉、内臓をひとつひとつ取り出しながら教科書で確認します。
私たち獣医学生のために命を捧げてくれた動物達にあらためて感謝です。
獣医っぽい専門科目が増えてくる:3年生
3年生から一気に専門科目の授業が増えます。生理学や薬理学、微生物学など、獣医学の基礎となるところを学んでいきます。
教養科目がメインだった1、2年生に比べると授業の難易度が格段にアップ!!
午前中は座学、午後から実習という毎日で忙しくなります。
忙しいんだけど、獣医の専門科目を学べるのはやはり楽しい。高校までの勉強や教養科目と違い、自分で選んだ専門なので当たり前ですね。
が…
試験は地獄だ。
何回も言いますが、時間とやる気のある低学年のうちから少しずつ専門科目を学べるようしてほしい!
単位を落とすと、留年。次の年に下の学年と一緒に試験を受けなければいけません。
とにかく単位を取ることに必死でした。
研究室へ配属:4年生
さて、4年生。前年の専門科目の怒涛の試験ラッシュを乗り越えて、だんだん専門科目の多さに慣れてくるころ。
4年生の後期には研究室へ配属されます。
基礎系、応用系、臨床系など、だいたい12、3の研究室があります。
私立大学はもっと多くて20個以上あるみたいです。
選ぶのが大変そうですね。
国立大学の場合、各研究室に2、3人ずつ配属されます。
基本的には自分の希望する研究室へ入ります。
ただ、人気の研究室もあるので、希望人数が多い場合は話し合いで決めます。
くじ引きという大学もあるらしい。
私の大学の場合、人気のない研究室が2個ほどあって、それ以外はまあまあ均等に人数が分散したので、そんなに揉めることはなかったです。
研究室を選ぶポイントは、私の場合ですが、その研究室の雰囲気、教授・先輩がどんな人か、忙しすぎないかという点でした。
研究室によっては、教授の研究の手伝いや授業の助手などを任せられることがあり、拘束時間が長いところもあります。
やりたい分野の研究ができるかどうか、将来の進路につながるかどうかで研究室を選ぶ人もいます。
製薬などの企業に行きたい人は、基礎研究をやっといた方が有利、とかありますからね。
でも逆に、「将来臨床の道に進むから、学生の間は全く異なる分野の研究室に入りたい」という人もいました。
獣医学科の場合、研究室で進路が決まるわけではありません。
直感的に自分に合うと思ったところがいいんじゃないでしょうか。
ポリクリ、そして卒論に本気で取り組む!:5年生
5年生のメインイベントはポリクリ。
4、5人のグループに分けられ、臨床系の各診療科を回って実習をします。
臨床系(実際に動物を診療する内科や外科など)の授業や感染症の授業が増えてきて、私はこの頃の授業や実習が一番楽しかったなと思います。
そして研究室では卒業論文のテーマを決め、本格的に実験を始めます。
研究室ごとに専門の研究があるので、代々やっている研究を先輩から引き継ぐのが一般的だと思います。
もちろん、やりたい研究がある!というのであれば、教授に相談してみてもいいでしょう。
約1年半で、実験をしつつ、論文にまとめ、卒論発表用にパワーポイントをつくるという作業を同時に進めていきます。


就活に国試にイベント盛りだくさん:6年生
6年生の3大イベントは、卒業研究・卒論発表、就職活動、国家試験です。
卒業研究・卒論発表
卒論のテーマが決まり、コツコツと実験を進めていくのですが...
なかなか自分が思うような結果がなかなか出ません(泣)
それでもなんらかの結論を出して論文にしなくてはいけないし…
果たして間に合うんだろうか?
夏休みぐらいから毎日研究室に行き、ひたすら実験してました。9月ごろにはなんとか論文が書けそうなぐらいのデータを集めました。
実験終わった!とのんびりなんかしてられません。
次は論文と発表用のパワーポイントをつくっていきます。
途中で追加実験が必要なこともあったり、とにかく焦る。
12月までには研究結果をパワーポイントにまとめ、12月中旬に学部生、院生、教授たちの前で発表。
今までで一番緊張したいやーな時間でしたね。
でも私の場合、今後は「研究」とはいっさい無縁になるので、貴重な経験ができたなと思います。
卒論の発表、提出が終わると、研究室で打ち上げをしたり、クラスの友達と旅行に行ったり、しばらく開放感に浸ります。
就職活動
就活は春ごろから始めました。
少し早いかもしれませんが、卒論の研究に集中するためになるべく早く就職先を決めたいという思いがありました。


国家試験
いよいよ6年間の締めくくり、国家試験(国試と呼んでます)です。
正月が終わったあとぐらいから、ぼちぼち国試の勉強を始めます。
獣医師国家試験は、8〜9割の合格率なので、普通に勉強すれば受かります。
ただ、この「普通に」というのが大事で、特別なことをやる必要はないのです。
全国の獣医学生が作った国試対策本があったり、過去問も出回っているので、それだけで十分。
科目はたくさんあるし、覚えることも山ほどあります。
1ヶ月半でとにかく詰めこみまくる…
そして、もう一つ大事なのが、家に1人でこもって勉強しないこと。
ここが大学受験と違うところだと思います。
たいてい何人かで集まって学校で勉強しているので、どれかのグループに入ってみんなで勉強した方がいいです。
国試はとにかく範囲が膨大なので、自分が的外れなところを勉強していないか周りをみて確認しながら、効率よく勉強するべきです。
友達と一緒なら分からなかったらすぐ聞けるし、友達同士が相談しているのを盗み聞きしながら、あぁそれはそういうことかぁ、と新たな発見ができたり、いいことづくめです。
学校に出てこず、1人で勉強している人もいましたが、あまりいい結果は出ません。
そして2月下旬、少し不安な気持ちも抱えながら、本番を迎えます。
緊張はしましたが、卒論発表に比べたらなんてことはなかったですね。
国試は2日間あり、東京、北海道、福岡の3ヶ所で行われます。
国試が終わると、実家で過ごしたり、卒業旅行へ行ったり、就職へ向けての準備を始めます。
就職先が決まってない人は急いで就活してました。
合格発表・卒業
3月上旬に国試の合格発表。
農林水産省のホームページ上で発表されるので、それを確認してから大学へ合格通知を受け取りに行きました。
先生方に祝福されて、だんだん実感がわいてきます。
そして、いよいよ卒業です。
6年間を過ごした大学、クラスメイトと離れるのはやはり寂しいです…
みんなそれぞれ獣医師として活躍するんだ、と心に誓い、卒業です。
まとめ
こんな感じで6年間を過ごしました。
学生の間にもう少しやっておけばよかったなーと思うことがいろいろありますが、とても充実した6年間でした。
今回はだいぶ短くまとめたので、授業や実習、就活についてなど、別の機会にあらためて書いていきたいなーと思ってます!
それではまた。



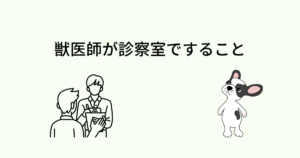
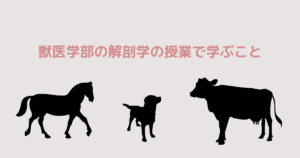


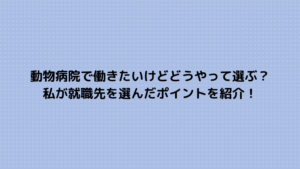

コメント