最近飼い始めたハリネズミ、こんな症状があるんだけど病院へ行ったほうがいいのかな?
ハリネズミが健康かどうかチェックするポイントがあれば教えてほしいな。
こんにちは、獣医師のにわくま(@doubutsu_garden)です。
年々飼育頭数が増えてきているハリネズミ。飼おうかどうか迷っている人も多いのではないでしょうか。
ペットショップで見かけることも多くなりましたし、動物病院への来院数も以前より増えていると感じます。
しかし、犬や猫に比べると、飼育方法やかかりやすい病気について知られていないように感じます。病気の早期発見や予防のためにも、病気のサインはぜひ知っておいてほしいなと思います。
今日は、ハリネズミの病気のサインとしてどのようなものがあるのか、どのようなところに注意してみればいいのかを解説します!
ハリネズミを診てくれる動物病院はある?
獣医師はすべての動物が診療対象なので、もちろんハリネズミも診察の義務があります。
しかし、実際はハリネズミを診療対象にしていない動物病院が多く、連れていっても断られる場合があります。
ハリネズミを診てくれる他の動物病院を紹介されることもあります。
ハリネズミを家に迎える前に、近くにハリネズミを診察してくれる動物病院があるか必ず確認しましょう!
ハリネズミでよくみられる症状は?
さて、ハリネズミが病院に来る理由は健康診断から下痢や皮膚病などさまざまです。
トゲトゲした針、これがハリネズミの最大の特徴ですが触るのはなかなかむずかしいですよね。
もし病気になったら、その異常に気づくのはなおさらむずかしいのでは…と心配する人も多いと思います。
しかし、ハリネズミに触らなくても、排泄物や行動、ケージの中を観察してみるだけでも、病気のサインをいくつも発見することができます。
それでは、実際にどんなところをチェックすればいいのでしょうか?
針が抜ける・フケが出る・体がかゆい
まずは皮膚の症状からみていきましょう!ハリネズミの場合は、針が抜ける、フケが出ているといった症状に気がついて来院することが多いです。
ハリネズミの背中には約5,000本の針があるといわれています。針は爪や被毛と同じように、ケラチンというタンパク質からできています。
他の動物の毛と同じようにサイクルがあり、だいたい1年半で生え変わります。1日に10〜20本は抜けるので、この範囲であれば心配することはありません。
これが40〜50本以上抜けているようであれば、異常です!
- ダニの寄生(疥癬)
- 真菌感染(皮膚糸状菌症)
- 細菌性皮膚炎リンパ腫(腫瘍)
- ストレス
- アレルギー
- 栄養不足
- 脂漏症
- 成長期にみられるクイリング
などがあげられます。
ハリネズミはストレスを受けやすい動物です。
飼育環境の変化、ケージの配置換え、ケージ内の温度の変化、騒音、来客など、私たちにとっては何気ないことでも、ハリネズミにとってはとても大きな変化に感じられることがあります。
ストレスによって「10円ハゲ」のように一部だけ針が抜けてしまうこともあります。
針が異常に抜けている場合は、まず、ストレスがかかるような出来事がなかったかを思い出してみてください。
ダニの寄生(とくに疥癬)もよくみられます。
すでにダニが寄生しているハリネズミと接触することにより感染したり、床材やタオルなどを介して感染することもあります。ペットショップやブリーダーのところで感染していることが多いです。
針の付け根の皮膚や目の周りをよーく観察してみてください。かさぶたのようなフケはないですか?また、ハリネズミがしきりに体をかゆがっていることはないですか?
ダニが寄生していると、針が抜けたり、大量のフケが出たり、激しいかゆみが出ることがあります。
もしこのような症状がなくても、家に新しくハリネズミを迎えた場合は注意してみてみましょう。
意外と知られていないのですが、ハリネズミは針葉樹(松やスギ)にアレルギーがあると言われています。
針葉樹のウッドチップを床材として使用している場合は広葉樹のものに変えるといいかもしれません。広葉樹にもアレルギーを示す子もいるので、ダメな場合は紙製の床材やペットシーツも選択肢の1つに入れておきましょう。
犬や猫でもそうですが、皮膚や被毛は多くのタンパク質を必要とするので、やはり栄養不足になると皮膚トラブルは増えます。タンパク質以外にもカルシウム不足も針が抜ける原因の1つになりうるので、コオロギなどをおやつとして与えるのもいいでしょう。
そして、ハリネズミの成長期(だいたい生後4〜6ヶ月)に、大量に針が抜けることがありますがこれをクイリングと言います。
一か所だけが抜けるのではなく、全身からまんべんなく針が抜けている場合はこのクイリングの可能性があります。成長とともに生えてくるので心配ありません。
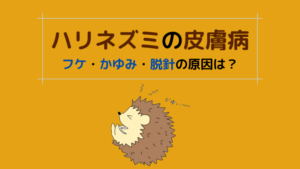
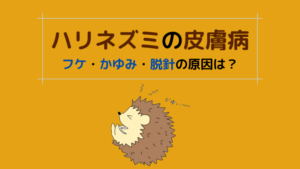
皮膚にできものがある
背中やお腹、顔にできものができることがあります。
腫瘍
まず考えられるのは、腫瘍。高齢になるほど増えてきます。
ハリネズミでは乳腺腫瘍、リンパ腫、口腔内扁平上皮癌、軟部組織肉腫などが報告されています。
悪性のものも多く、早期発見が重要です。
病理学的には犬や猫と同じ腫瘍でも、エキゾチックアニマルの場合はわかっていないことも多く、治療の判断が難しいこともあります。
膿瘍
次に、膿瘍。
膿瘍とは、組織の中に膿がたまった状態をいい、できもののように腫れ上がります。
傷口などからの細菌感染が原因となることが多いです。
また、歯周病が原因で起こる根尖膿瘍で顔面が腫れることがあります。
血尿している
血尿していて、それがメスだった場合、出血が膀胱からなのか子宮からなのかを見分ける必要があります。



ちなみにハリネズミに生理はありません。
- 卵巣・子宮疾患
- 泌尿器疾患
もちろん膀胱結石や膀胱炎などの泌尿器疾患もありうるのですが、ハリネズミ、とくにメスの場合は子宮からの出血であることが非常に多いです。子宮の腫瘍や子宮内膜炎、子宮内膜過形成が原因となることが多いです。
この場合、卵巣・子宮を全摘する手術をおこないます。
出血量が多いと命に関わるので、血尿が出たら様子を見るのではなく、早めに病院を受診しましょう。


よだれ・口から出血・顔周りが腫れている
ハリネズミは触診するのがけっこうむずかしいのですが、口の中をみるのはより一層むずかしいんですね。
なので、詳しい検査をするには麻酔が必要となることが多いです。
顔周りや口のトラブルで多いのは歯周病や腫瘍。
歯周病
雑食性の高いハリネズミは、歯周病が多くみられます。
歯と歯肉の間で細菌が増殖し、歯肉炎を起こすと、歯肉がとけて歯がぐらつきます。
そこからさらに細菌が入り込み、顔面が腫れたり、膿が出ることもあります。(根尖膿瘍)
腫瘍
ハリネズミでは悪性腫瘍である口腔内の扁平上皮癌が多く報告されています。
初期では、歯肉炎と区別がつきにくいので経過をみていく必要があります。
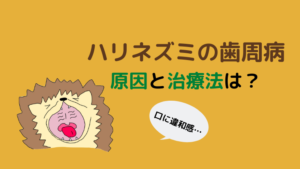
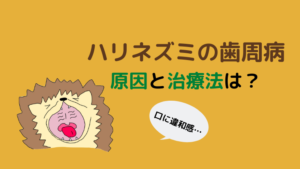
下痢をしている
ハリネズミの正常な便は茶褐色から黒色で、バナナのように細長い形をしています。
- 不適切な食事
- 細菌性腸炎
- 真菌性腸炎
- 寄生虫性腸炎
- 腫瘍
下痢の原因として一番多いのは食事によるものです。
普段与えないものを与えたり、急にフードを変更したり、思い当たることはありませんか?
もう一つ注意してみてほしいのは、「便の色」。
正常な便は茶色ですが、「緑色の便をしている」時は何らかの原因で食事がうまく取れていない可能性があります。
ハリネズミは食欲不振による濃緑色の軟便、下痢が多くみられます。その場合は食欲不振の原因をつきとめていくことになります。
下痢が続くと脱水を起こしたり、さらに食欲がなくなったりするので注意が必要です。


食欲がない
食欲不振の原因は大きく分けて2つです。
- ストレス…家に迎えたばかり、飼育環境の変化、フードの変化、移動・輸送ストレスetc
- 何らかの病気…口腔内疾患、腎疾患、肝疾患、腫瘍etc
ハリネズミは警戒心が強く、ストレスに弱い生き物です。ストレスになるような要因はいくつかあるのでちょっとした変化でも食欲不振に陥ることがあります。
まずは詳しく問診をして、ストレスになりそうな出来事がなかったか、あれば改善して様子をみます。
そして視診、触診から糞便検査、尿検査、血液検査など何か病気が隠れていないか調べていきます。
立てない・歩けない
- ハリネズミのふらつき症候群(Wobbly Hedgehog Syndrome ; WHS )
- 変形性脊髄症
- 変形性関節炎
- 骨折
ハリネズミのふらつき症候群は2歳以下のハリネズミでの報告が多いです。
初期は丸くなれないという症状から始まり、ゆっくり進行していきます。
数ヶ月で完全麻痺になり、最終的には死亡する病気です。
根本的な治療がなく、QOLを維持するための強制給餌や点滴をしていきます。
変形性関節症、変形性脊椎症については、高齢のハリネズミにみられる神経系の疾患です。


お家でできる健康チェックとは?
ハリネズミは体が小さく、犬や猫と違って体調の変化に気づきにくいです。
さらに、いざ病院へ連れていっても、移動のストレスで病院に着いたときには丸くなってしまい、診察が難しいこともよくあります。


こんな感じ・・・
獣医師もよく視診、触診をおこないますが、飼い主さんからの情報も重要になってきます。
そこで、お家でできる日々の健康チェックを紹介します。
- 食欲があるか(食べ切っているか把握できるぐらいの量が良い)
- 急激な体重の変化はないか(週に1回は体重測定できると良い)
- 便・尿に変化はないか(色、量、軟らかさ)
- 体をかゆがっていないか
- 針の根元にかさぶたやフケはないか
- 顔や目の周りが粉をふいたようになっていないか
- 皮膚に炎症はないか針が大量に抜けていないか
- よだれはないか
- ふらついたり、足をひきずったりしていないか
直接触ってチェックするのは難しいかもしれないので、透明のプラスチックケースに入れてよく観察するのもいいですね。
まとめ
最近はハリネズミを飼う人が増えてきて、診察でみる機会も増えています。
ハリネズミについてはまだ知られていないことも多く、獣医師も苦戦するところだと思います。
少しでも早くハリネズミの変化に気づくようにするためにも、飼い主さんの日々の健康チェクが非常に重要です!
ぜひ参考にしてみてくださいね。

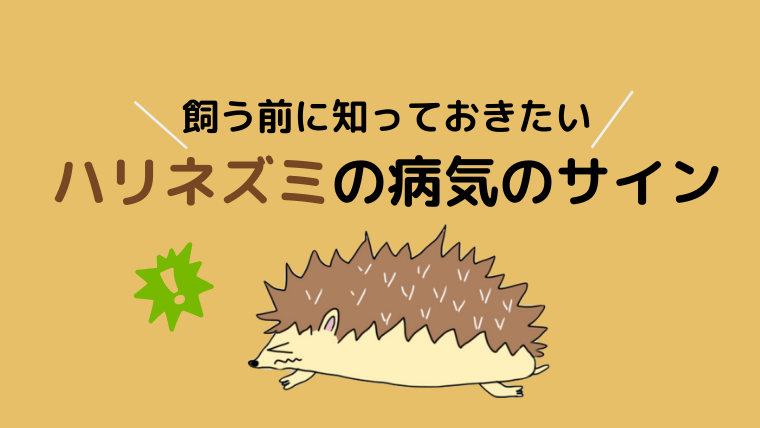


コメント